プレイヤーの分身にして本作の主人公。MOTHERではニンテン。名前の由来は劇中(悪夢の中の)ママが語っていた「いつもニコニコしていて欲しい」という意味のほかに、BUMPのマスコットキャラクター(?)マフラーをした猫、ニコルくんのもじりでもあります。バットを振り回して敵をなぎ倒していく乱暴者にも見えますが、バトル後のメッセージをよく読んでもらうと、彼が決して生き物の命を奪うことなく旅を続けているのがわかると思います。強くてやさしい子なのです。
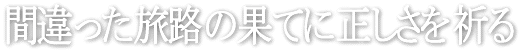
この作品を愛してくれたすべての「あなた」に
ありったけの愛を込めて、オマケを
あとがき
カーテンコール
ニコ
リリィ
もうひとりの主人公。物語のテーマやモチベーション、その他ありとあらゆる事物の主。MOTHERではアナ。名前の由来はBUMPの『リリィ』から。後半の彼女の手紙を書くとき、一週間くらいかけて「自分がもうすぐ死ぬと悟った小学生の女の子」の気持ちになろうとイメージトレーニングをしました。手紙後半部分の叫びにも似た部分は、そのイメトレの結果生まれた部分。「それだけが私の望み」って言ったすぐあとで、堰を切ったようにニコに向かって別のお願い事を一杯してしまう矛盾は、本当は「死にたくない!」と叫びだしたいのを我慢しながら、それでもどうしてもお行儀よくしていられなくなってしまって泣いてしまったというイメージなのです。
アルエ
どこか隠れキャラっぽいメインヒロイン。名前の由来はBUMPの『アルエ』から。一説によるとアルエとは「RA」のことで、『新世紀EVANGELION』の「綾波レイ」のイニシャルだとか。劇中のアルエは『アルエ』に描かれている女の子のキャラクターと綾波のキャラクターをミックスした存在になっています。ちなみにブランコのアルエはアンクルオン研究所でニコと出会って、その後ロキに時空の果てに飛ばされ時間を逆行してきたアルエ(ファースト)。そのあとアスガルドの病院にやってきたのがアルエ(セカンド)。トゥルーエンドで青い石を使って時空の果てから呼び出し、最後にニコと一緒にいるのはアルエ(ファースト)です。ごく初期の段階ではこのキャラクターにさらに『MOTHER』のフライングマンの要素も入れようとしていました(わかる人はわかると思いますけど、恐ろしい話ですよ。ボツにしてよかった……)。
ベル
ニコの妹。MOTHERではニンテンの妹のミニー&ミミー(双子)。名前の由来はBUMPの『ベル』から。好きなキャラなのに微妙に影の薄い存在になってしまいました。でも銀河鉄道の彼女のセリフは自分で作っときながら、ちょっと泣けます。かわいい妹です。本当は旅の先々で電話をチェックすると自宅のベルが次の目的地や謎解きのヒントをしてくれるようにするつもりだったのですが、イベント容量の都合で泣く泣くカットせざるを得ませんでした。本当は「Tipsチップス Ver3」も後半に出したかったんだよなー。
ママ
ニコのママ。MOTHERでもニンテンのママ。「いてらさい」は「いってらっしゃい」のママ流の言い方。あと喫茶ビッグロックのマスターのことはただの友人としてしか見ていません。あと実はニコのパパはゲームの中に登場しています。さあだーれだ! ちなみに後半の酒場のママも同じグラフィックなのですが近くで見ると似ても似つかない顔のはずです。あの酒場のママは誰が見てもその人のママみたいに見えるという大人のファンタジー、男はたぶんみんな一生マザコンでしょというお話。
天体望遠鏡
アイテムのドット絵はすべて自作です。ってこれはアイテムじゃないですけどね。ぼくはデザインのセンスがまるでないので、現実にあるものをスケッチすることしかできません。なのでこの望遠鏡にもモデルがあります。どのアイテムもイメージ検索とかかけるとすぐにモデルが見つかると思うので、暇な人はモデル探しをしてみると面白いかもしれませんヨ。
リリィのパパ
リリィのパパ。アンクルオンの孫(だっけ?)。アンクル生物たちの存在を基本的に認めておらず、リリィクローンのアルエには特別冷たい人です。ただ別に、この人が悪人だってわけじゃなく、一般的な人工生物に対する反応としてああいう描き方をしました。それから実を言うと銀河鉄道の車内で彼の語ったことがこの物語でぼくの言いたかったことのすべてだったりします。魂とか死後の世界とかまったく信じていない人でも、生き残った人は死んだ人がどうなったのか自分自身の心の中で決めてしまわないと――決めておかないといけない。そうしないと本当に大切な人を失った時に、生きている人のほうの時間も止まってしまうんじゃないかと思うのです。「死んで星になった」というのは単なるロマンチックや子供だまし以上の意味があると思うのです。
少年
プレイヤーがたぶん一番初めに話しかけるであろう知らない人。どうしてわざわざこの少年のトピックがあるのかというと、彼のセリフにこそ、このゲームの演出の真髄が隠されているからなのです。なーんてそんな大げさな話でもないんですが、要するにゲーム始まってすぐに姿を消してしまうリリィのキャラ立てをどうやってやるのかということで、ぼくは色々悩んだ末に、彼やその他の脇役たちに、リリィとニコとの関係、彼女のビジュアル性、周りからどう思われるような娘だったか、などをそれとなく語ってもらおうと考えたわけです。その役割はホセとかダチとかにも振ってありますね。この辺りの演出は、失敗した試みの多いこの作品の中でそこそこうまくできたなあと思う部分です。
ホセ
ホセの名前の由来はBUMPのメンバー増川弘明氏(Gt)のニックネームから。痩せているので「細ぇ」→「ホセ」という意味らしいです。序盤のホセのセリフは無駄に凝ってますね。七五調ですよ無駄に。別名とうせんぼジジイ。あ、あと、入れるドアと入れないドアのアイデアはニコリリオリジナルではなくてMOTHERからの流用ですよ。
オージロー
ホセの奥さん。名前の由来は増川氏の飼っている犬の名前おおじろうから。尾の白い犬らしい。経営者として非常に有能で、ホセハウジングは彼女のおかげで持っていると言われています。ヒカゲ荘の住人からは家賃回収の鬼と呼ばれ恐れられているとか、ニッケはそんな彼女の督促を神がかり的なテクニックでかわしていたとかいないとか……。
リリィの家の鍵
プレイヤーが最初に手に入れるアイテム。家の鍵を不動産屋さんが管理してるのは現実世界ではものすごく当たり前の話だけど、このことを再現したRPGは見たことがありません。なんでこんな変なこと思いついたのか、今ではどうしても思い出せません。BUMPネタではなかったはずですが……。ちなみにどうでもいい話ですけど、このドット絵は自分の家の鍵を見ながら打ったものです。
ダチ・ポテコング・ミソッカス
ダチは友達のダチ。ポテコングは「ゴリライモ」とか「ジャイアン」とか「ブタゴリラ」とかの系譜のネーミングを考えていて不意に思いついたもの。BUMPのメンバーの大好物がポテロングかどうかは知りません(そうだったらいいけどなー)。ミソッカスは最近の子はあまり言わないかも知れないけど、子供のグループの中で年が小さい子が混じってたりする時にそう呼んで、鬼ごっことかの遊びでハンディを与えてもらえる存在。大人から見た子供時代の憧憬みたいなイメージの呼称、ですかねー。あ、あとaruさんの描いてくださったファンアートに、この連中とニコとリリィとベルが「タカオニ」をしてる絵があって、それがものすごーくいいカンジで、ちゃんと体の弱いリリィがベンチに座ってたりとか、ダチがニコにしてやられてたりとか、もうこんなとこ読んでる暇があったらおめーらいっちょその絵見てこいや!ってくらい好きな絵。
おねいさん・彼女に思いを寄せる少年
図書館のあの人は「おねえさん」ではなく「おね“い”さん」。固有名詞です。ある意味、裏ヒロインとも言えるくらい重要なキャラクター。誘拐事件後、重いPTSDを負っていて、その原因については劇中意図的にぼかしてある部分なので、ここでもはっきりしたことは書きたくないのですが、わりと大人向けにターゲットを取っていたマスターシナリオの名残がちょっと残ってしまった展開ではありました。工場でニコが話しかけてるのに「ビクッ」って怯えたりとか、ちょっと生々しくしすぎた感もありますね。要は子供に対して大人は強がり続ける義務があって、それでもつらいもんはつらいんだよというお話。ストーカーチックなあの少年に今後の彼女の支えになって欲しいと願うのは反社会的な考えでしょうか?。
喫茶ビッグロックのマスター
ビッグロックの名前の由来はBUMPのメンバー直井由文氏(Ba)の実家、居酒屋「おおいわ」から。このマスターはニコのママを狙っていて、その下心からニコに親切にしてくれています。ジョルノのジェット機でサクラ市を旅立つ直前にこのマスターのセリフを見てしまうと、ママの身があまりに気がかりでどうにも旅立つのを躊躇してしまいませんか(笑)? ぼくはそうです(笑)。
コンビニ店員
MOTHERではハンバーガーショップの店員。このキャラについては特になにも語ることがありませんが、コンビニの棚のドット絵は自分で言うのもなんですけど非常に労作。変則的に縦長の画面になってるので遠近感を取るのに角度にこだわったりだとか、ニコの画像との重なり合いの部分で、買い物システムに関わっているので単なる背景にもできず、書き換え処理を無理やり割り込ませたりとかしていて、ものすごい無駄に容量食ってしまってます。まあでもそういう無駄なこだわりが自作の中ですごく好きな部分だったり。
気功師範・気功仙人
気功の三ジジイの名前の由来はBUMPの『オンリーロンリーグローリー』から。三人は実は兄弟で、オンリーが長男、ロンリーが次男、グローリーが三男です。ポテコングは仙人と親戚ってことですね! ちなみにBUMPのメンバー藤原基夫氏(Vo&Gt)は常日頃から仙人になりたいと言っているそうです。ところで今考えると、ヒゲがもともと生えてるのになんでヒゲメガネを欲しがるのかオンリー仙人。
ニッケ・ジョルノ
ニッケとジョルノの名前の由来はBUMPのメンバー増川弘明氏(Gt)のニックネームから。増川氏が「日経とJALの二人旅」を「ニッケとジョルの二人旅」と読み間違えたことから「ニッケ」と「ジョルノ」というニックネームがついたとか。貧乏と金持ちのふたりの絵描きというキャラクターの設定はBUMPの『ベストピクチャー』からですが、歌詞ではこのふたりが別人であると明確にされているわけではないので、時間のずれた同一人物である可能性もあります。それを踏まえてのニッケとジョルノというネーミング(どちらも増川氏ですから)。
ホーリーナイト(シリアルナンバーK)
ホーリーナイトの名前の由来はBUMPの『K』から。貧しい絵描きが黒猫を拾い、やがて死に、手紙を託された猫もそれを届けた後に死んでしまうという展開も『K』を踏襲しています。ちなみにサクラ市の駅前通り「シューマーツノ大通り」という変な名前は『K』の出だし「週末の大通りを黒猫が歩く」から。あと気づいている人も多いかと思いますがホーリーナイトは「*Reprise」で超重要キャラとして登場してます。
猫のヒゲ
グローリー師範曰く勇気の証。某有名RPG1で上級職にクラスチェンジしたかったら勇気の証を取ってきなさい、というイベントがありまして、そのとき手に入れるアイテムが「ネズミの尻尾」でした。そこからの発想。ちなみにテスト版ではヒゲを無理やり抜いてホーリーナイトが怒るという流れでしたが、テスト版をプレイした小学生の女の子が「猫がかわいそう」と言っていたのを見て「まったくそのとおりだ」と思い、「今にも抜けそうな」ヒゲを頂くという流れに変えました。ニコリリは猫好きです。
ナース
今はもう看護婦って言わないんですよね、看護士なんですよね。で、その看護士という呼称にどうにも違和感を覚えてしまうので、劇中はナースという呼び名で統一。極端にビジネスライクなナースと、まさに白衣の天使というべき性格のナースの二種類を登場させました。天使ナースのセリフなんか3〜4種類くらい書いた気がします。普通にプレイしてる人はたぶん気が付かないような場面。力入れすぎた(笑)。
怪しいクスリ
旅のガイドで遠まわしに明らかにしてますが、いわゆる持ってるだけで捕まっちゃう系のクスリです。サクラ市のダークサイドというわけです。もちろんデパートで売ってるのは中身が違っていて合法なヤツですが、バイニン(買人)は目が利かないので簡単に騙されます。ちなみにこのドット絵は近くにあったクスリのビンを見ながら打ちました。
見かけだおしではない帽子
こういうネーミング好きなんですよね。これを装備しない状態で工場に入ると、ブレイバーに「その帽子、見かけだおしもいいとこだな……」って言われちゃうんですけど、たぶん普通にプレイしてると帽子を手に入れるほうが先ですよね。それだとブレイバーの台詞は見られないわけで、そういう因果関係が捻じ曲がった感じが作り手としてはあとからニヤニヤしたりの部分です。
ブレイバー(ジョイ)
頼りになるアニキキャラ。MOTHERではテディ。男の子プレイヤーの一番人気です。こういういかつい奴に認められるようになるということがニコくらいの男子にとってはこの上なく痛快なわけですよ、少年のファンタジー。名前の由来はBUMPの『リトルブレイバー』から。幼名(?)のジョイはBUMPの隠しトラック『In my heart』と『In my NIKKE』を唄っている架空のグループ「joy」から。世界樹の民の出身で聖地の守人としての限界を超えるべく、若い時に武者修行の旅へ。レムに辿り着いた彼はやがて都会の絵の具に染まっていった……。意外とこの辺の説明は劇中で端折っちゃってますね。時間を飛び越えまくる反則的なキャラなのでちょっとここで整理すると、一番若いのが酒場の用心棒のジョイ(17〜18くらい)で、次に若いのがロキがニコを懐柔しようとしているところに助けに来るブレイバー(20代)。そしてエンディング後のあとの時代からニコの要請によって子供ニコを助けに来たのがおっさんになったブレイバー(30歳くらい)です。おっさんのブレイバーが仲間になってる状態で家に帰るとママが不審そうにします。あ、そうだ、「おらが闘争」の著者でもありましたね。
ヘビとかネズミとか
RPGにはなくてはならない存在。スライムとかゴブリンとかプノトンとかミジンコとか。コンビニ店内にいるお兄さんが、サクラ市のヘビやネズミは全国一凶暴だという話をしてますが、あれはいちおう公園の奥の旧アンクルオン研究所から逃げ出した実験動物たちが野生化しているという設定の伏線だったりします。敵が(メッセージ上は)現金を落とさない国外編と違って、サクラ市街のネズミはなぜか現金を持ってます。都会のネズミはすごいですね。
バット
主人公の装備する武器がバットというのはまんまMOTHERを踏襲しています。なぜか金属バットは持たせたくなかったので、いちおう出てくるバットは皆プロユースのレプリカです。デパートで売ってる値段はほぼ現実世界どおりなのですが、手に入れにくさ、あるいは入れやすさがちょうどいい感じにできたので、作ってる最中、妙に嬉しくなったのを覚えています。
ロストマン
序盤の敵役、終盤の旅の仲間。MOTHERではロイド。名前の由来はBUMPの『ロストマン』から。詳細は下記「ロストマンのこと」参照。悪役が「フッフッフ」とか「フハハハ」とか笑う演出には意味がないと思っているので本当は嫌いなんですけど、セリフ考えてる時、こいつは「クックック」とか勝手に言いだすのでやっかいでした。こういうクールっぽい悪役のセリフってのはスラスラ出てくるんですよ、内容は空っぽですけど。初登場時のセリフはたくさんしゃべらせた後で半分くらい削除しました。あとね、タンポポの匂い、本当は好きなんですよコイツ。その匂いの好きな自分自身のことが嫌いなんでしょうね、きっと。
スパイクシューズ
ナイキでなくプーマかアディダス。たぶん物語を進めるためにお金を払って購入する必要がある最初のアイテム(だったはず)。あえて登山靴とかピッケルとかでなく、普通のシューズとしてお店に置いておくことで、ほんのり謎解き風味にしてあるわけです。怪しいクスリを順序良く売った人にはさほど高価な買い物とならないように設定してありますが、テストプレイとか実況動画とかを見ると、やはりここでネズミ狩りを開始する人が圧倒的に多かったみたいです。
シリアルナンバーM
ロストマンによるシリアルナンバーK発見の報を受け、命令も待たずにこの地へやってきたアンクルオンの刺客。知能昂進のほかに闘争本能の増幅もされている。Kとは研究所時代からライバル関係にあるが、試験の成績はKのほうが常に若干高い――。なんていう漫画みたいなベタな設定の敵役。ニコに敗れてからは打倒ニコが人生の目標になりますが、生きることが闘うことのこのサルにとっては憎しみも敵愾心も友情も愛もすべて一緒くたなわけで、要するにKやニコのことをこの上なく愛しく思っているという妖しい存在です。
アナ
ニッケが故郷に残してきた恋人。MOTHERではピッピのママ。アナという名前はMOTHERのアナではなく「ANA」。ニッケとジョルノの由来が「日経とJALの二人旅」なので航空会社つながりということでこの名前に。「Holy Night(聖なる夜)」を「Holy KNight(聖なる騎士)」と一字付け足してお墓を作るというのはBUMPの『K』に出てくるあまりにも有名なエピソード。
雪ダルマ
こいつのメッセージについては、いろんな人からいろんな感想を頂きました。製作後半、世界観を成立させるために役に立っていないメッセージは見つけ次第思い切り削っていたので、だいたいどれもなんらかの必要性があって残したものばかりですが、これはなんとなく消すのを忘れて最後まで残ってしまった数少ない「素のニコリリの言葉」です。プレイヤーによっては違和感を覚えたことと思いますし、そのことで強く印象に残ったんだと思われます。 このメッセージを好きだと思ってくれる人とは、きっと仲良くなれると思います。
リンゴ バナナ ニンジン
シモエルさんの実況で、コンビニの生鮮食品はABC順というヒントの意味に気づいててくださってて、すごくうれしかったですねー。ちなみにゲームに登場する全てのアイテムのうち、リンゴだけが「なんの意味も持たないアイテム」です。一応サバンナでゾウに与えてどかすことができますが、あれはバナナでもニンジンでもどくんですよね。まああれですよ、逆さ柱とか眠り猫みたいなもんですよ。
ラプンツェル
オフィスジョルノの受付嬢。名前の由来はBUMPの『天体観測』の歌詞が出来上がる前のドラフト名から。DVD『jupiter』で変な踊りと共に「ラプンツェル」を唄っているのを聴けます。ラプンツェルとは直訳すると菜っ葉のことですがグリム童話のヒロインの名でもあります。ジェット機墜落後のジョルノとラプンツェルを襲う悲劇的な展開はBUMPの『Ever lasting lie』を踏襲しています。心が強い絆で結ばれ続けているのも歌どおり。ちなみにサンドシー砂漠の名前の由来も『Ever lasting lie』の出だし「砂の海で錆びたシャベルを持って」から。
インスタントカメラ
写メールというものが携帯に付くちょっと前くらいに、女子校生の間で流行っていた、撮ってその場ですぐ見られる写真が取れるカメラです。意外と味のある画が撮れます。前はコンビニによく置いてありましたが、今はなくなっちゃいましたね。最近はドンキホーテで売ってるのをみかけました。商品名でいうと「チェキ!」。
隠れウサギ
ミニゲームと呼べるほどのものでもないですけど、雪山にせっかく広いMAP作ったんで、プレイヤーにちょっとウロウロしてもらおうかと思って作ったイベントです。ここで思いついた絵と音のエフェクトが容量圧迫しないでうまくハマることがわかり、製作後半、あちこちに流用した覚えがあります。
春紫苑(はるじおん)
若い頃のジョルノがよくスケッチしてた花。由来はBUMPの『ハルジオン』から。歌詞によると「白くて背の高い花」とのこと。最強の武器を手に入れる条件(≒トゥルーエンドの条件)として、“花を踏まない”というのは製作初期から構想していたんですが、春紫苑を手折ることなく、写真におさめてジョルノに見せるというアイデアは、我ながらよくこんな変なイベント思いついたな、と感心したり。
トレインパス
今は無きパスネットですよ皆さん、って言っても首都圏在住の大きなお友達にしかわからないか、っていうシロモノ。切符からスイカとかのICカードへ移行するちょっと前にあった、磁気カード型の回数券&定期券です。そうかこのゲーム作ったのって5年も前なんだ……。
ジュピター
ジョルノの自家用ジェット。ていうか絵描きで自家用ジェットって、なにをどうしたらそんだけ金持ちなれるんだ? 名前の由来はBUMPのアルバム「jupiter」より。ほとんどの人が気がついていないし、まだ一度もばらしたことない話をすると、主人公を乗せたジェット機が空中で爆発するのは実はゲーム「たけしの挑戦状」へのオマージュ。左から右に飛んで行く画面のイメージもそのままです。
マーム
純粋であることと善良であることとはイコールではない、という存在。かといってそれは悪なのかというと、それもまた違うんじゃないかとか……。ティンパスト教団最強のクレリックにして、指導者ペニー神父の秘蔵っ子(実子かどうかは想像にお任せします)。虎だろうがソドップだろうが一撃で屠る体術を使いこなすクレリックという設定は、映画「リベリオン」のクラリックから(というかそもそもクラリックという言葉の元ネタがクレリックだとは思うが)。
聖地の人々
彼らの話す変な言葉は、BUMPの隠しトラックでいくつかある日本語に聞こえないヘンテコな歌詞を聞き取ったもの(人によっては違うように聞こえるかもです)。ちなみに設定的には「ヒンタボ語」という言語(ヒンタボ語を知らない人はとりあえずググってみてください)。ニコに感情移入しているプレイヤーには結構辛い彼らの言葉。実際はニコの責任じゃないのに、彼らがニコを責め立てるというその理不尽さは、実は彼らの平穏な生活が突然踏みにじられた理不尽さのそのまんまの裏返しというところに冷静に気がついて欲しいニコリリなのでした。
長老
とりあえず見た目がおかしい、なんだこいつは。MOTHERでは宮廷道化師。異世界の人なので、まあこの絵で長老もありかな、と。今更気づいたんですが、製作時は長老と村長と完全に混同していた気がします。聖地の人は皆そうですが、セリフはマームが同時通訳している設定なので、わざと翻訳っぽい文体でしゃべってます。
ラッキー落花生
まちたびのゲーム性を背負って立っていると言えるかもしれない存在。豆でなくてもなんでもよかったんですが、BUMPの隠しトラックに(名前だけ)出てくるバンド名から取りあえずこれに。回復とレベルアップとの要素を兼ね備えたハイブリットなドーピング剤。ドラゴンボール世代には仙豆という刷り込みがあるので、意外と違和感ないかも。
タランチュラ、イーグル
200円相当の砂金を隠し持っている大グモと、400円相当の風切羽を隠し持っている大ワシ。バトルで主人公が成長していくというのはRPGの醍醐味なのですが、まちたびでは「敵を倒す」という概念をなるべく排除したかったので、基本的には常に「大自然VS人間」の図式になっています。一部の例外を除いて「○○を倒した」というメッセージは出ないようになっているのです。
ノーリーズン
ドット絵は作成当時はお気に入りだったんですが、今見るとシズル感が足りない。ぶっちゃけて言うと要するにコーラなんですけれども、前にテレビ番組でチャラい若者がコーラのことをこう呼んでるのを見て印象に残ってたのでこの名に。CMのキャッチコピーでこう言ってたんですよね確か。一応BUMPの『ナイフ』の歌詞にもちなんでますが。
砂漠を越えてやってきた人々
聖地の持つエキゾチックな雰囲気には観光地としてのバリューがあると見込んでこの村をテーマパークにしようという野望を持ったエージェント。そのとっかかりとして説得され無闇に進出してきたコンビニチェーンの専務。村の子供に「ヨコシマ」と断じられている方々。でも店員さんは必死に地元の言葉を覚えようとしていてかわいい。ノーリーズンは観光地価格の設定でバカ高い。ここで買ってはいけません。
ジーバーガー
なんかこういう形の帽子のイメージで検索して名前をつけたんですけど、普段まったく帽子かぶらないんで、未だにこれあってるのかどうかよくわからないんです。
ピーナツおじさん
わりとあちこちに現れる、背景がまったくもって謎な人物。「¥」を「LIFE」にリソース変換するゲームシステムとしての根幹の部分。それをショップとかシステムメニューとかじゃなくて謎のおじさんが司ってるところが、すごくこの作品らしい(笑)。一瞬、猿が代理をすることもありました。ちなみに志村けんさんがボイスを当ててるイメージで喋らせてます。
ミレニアムビーフ
ラッキー落花生の上位互換。非売品で世界に2つか3つくらいしかない。落ちてる肉食べるの勇気いるなぁ。元ネタはチャマこと直井氏が雑誌で連載していた漫画のタイトルから。
ライオン
初見時「ニンゲン……」とか意味ありげに喋りかけてくるわりに、その後ニコとは再会することなく、いつの間にか自身の作った王国でお墓の下に埋められてる百獣の王。アンクル生物ではないんだけど、例の石の沈んだ川の水を飲んで賢くなっています。元ネタはBUMPの『ダンデライオン』。黄色の石=歌詞に出てくる「金色のコハク」かな? 元曲通りサバンナのみんなに嫌われてましたけど、死後、再評価されています。王国のエピソードはニコががっつり関わる案もあったんですけど、砂漠越えた先でのイベントが渋滞しちゃうので(位置も遠いし)、裏でいつの間にか進行してるイベントにしました。
マジックバタフライ
マジックバタフライ? そんなまんまパクリな名前つけちゃってましたっけ? 作中、移動するNPCはこいつとアスガルドのキバだけでしたかね。こいつに崖の上とかに逃げられたときの悔しさといったら……。いや別に採らなくてもクリアはできるんですけど……なんか悔しい。
シンジョー
これをゲットするタイミングはトゥルーエンド目指してる場合、ちょっと難しいですね。サクラ市から持ってきたサッカーボールをレム市の少年に渡してからじゃないと、アイテムのスポーツ用品欄が上書きされちゃう。って、このページを見てる方はそんなことはとっくにご存知でしたっけ。新庄剛志モデルのレプリカ。
サバンナの動物たち
この辺から現実的には小学生がバットで戦える相手じゃなくなってきます。つまりニコのヤキウの戦士としての力が覚醒しているという。ちなみにフラミンゴの尾羽を取るまでは普通に話しかけられます。だいたい鳴き声を話すんだけど、どう鳴くのか知らない動物にはなんか適当なオノマトペを放り込んどいた記憶(笑)
ゾウ

結構大きなSE(鳴き声)が鳴ります。びっくりしちゃった人いたらごめんなさい。フラミンゴの尾羽を取った後、果物をあげるとどいてくれるんですけど、ここで果物失うのはトゥルーエンド未達フラグですね。話しかけるたび足踏みするのかわいいな。
ハンター
衣食のためとか害獣駆除とかなら全然いいんですけど、スポーツ感覚で動物を撃ち殺す奴マジでなんなの? 軍人のおえらいさんとかが趣味にしてるイメージ。普段からそうやって生き物の命に対する感性を麻痺させといて、いざ有事の時なにするつもりなの? とかそういう偏見があるので、作中でひどい目に合わせちゃいました。
パズー
天空の城ラピュタの主人公がかぶってるような帽子。BUMPにもMOTHERにも関係ないんですけど、ラピュタ好きすぎて何回見たか覚えてないくらいなので、無意識にやってるラピュタネタが結構ある気がします。序盤のリリィパパのセリフとかね。
ラクダ使いとイカ(←ラクダの名前)

便利なタクシー。これに乗ったときの一枚絵は This is ドット絵!って感じで、海外の人にもプチ人気。ラクダのわけわかんない名前「イカ」はBUMPの隠しトラックから。とはいえ元ネタもラクダには全然関係ないし、なんでこれをチョイスしたのか自分でも全然覚えていないので、永久にわけわからんままです。
謎の男
初見時のNPC名これであってましたっけ? とうせんぼしているようでいて、単にニコの旅の手助けをしてくれる人物。詳しくは後ほど……15年越しの超重大情報込みで……。
パンダとペンギン
レムにたどり着いてすぐ、いきなりアンクルオンが見つかって「うおお……!」ってなってるプレイヤーの前に立ちふさがる最強アンクル生物!ではなくって漫才コンビ。てゆーかアンクルナンバーってシリアルナンバー(通し番号)であって動物名の頭文字じゃねーでしょっていうね。いやいや決してその設定を忘れてこいつらのダイアログを書いてたわけでは……。
ポキール市長
レム市の市長。有権者でないものには興味がない方。でもレム市の問題はちゃんと順番に解決していくので、仕事はきちんとする男の模様(実際働いてるのはニコですが)。ところでノベル「*Reprise」を読むとわかるんですけど、先代の市長って暗殺されてるんですよね。それにしちゃ市役所のセキュリティゆるすぎないすか……(笑)
カフェの人々
ラスト間際の展開に関する重要情報を話してくれます。みんな気づいたかわかんないですけどオープニングの天体観測で見てる彗星「旅のガイド」で名前確認すると実はラスボスなんですよ。そういうのが好きなんです。
リトルギャング
これもノベル「*Reprise」に詳しい、レム市の名物、幼いストリートギャングたち。とはいえ砂漠越えを果たした歴戦のツワモノであるニコの敵ではない、、、はずなんですけど、普通のNPCだと思って話しかけていきなり戦闘になってびっくりしちゃった人いましたらごめんなさい。
日本人サッカー選手が好きな子たち
言及されてる選手の名前が時代を感じさせますね。15年前かぁ……。なお「旅のガイド」のインタビュー風後日譚は書いててめっちゃ楽しかった思い出(まあ旅のガイドは、だいたいどれも書いてて楽しかったやつばかりですけど)。
ラプンツェルの仕事仲間(ライバル?)
WWAというのが(当時の)小中学生を中心にしたコミュニティっぽいというのは理解していた上で、このキャラとかの意味がわかるおませさんにだけ伝わればいいかな、という気持ちで『Ever lasting lie』の元ネタ通りの設定を入れてるんですけど、当時どのくらいのプレイヤーにこの辺の意味が伝わったんでしょう……気になります(←気功でダイエットしたい人の言い方)。
イチロー
ブレイバーからニコへのプレゼント! 言うまでもないですけどイチローモデルのレプリカです。
オゴマメ教授
名前はBUMPの隠しトラックから。ソドップ調査隊を聖地の山に派遣した人物。なんかすごいIQがとてもすごくてものすごいので、なんにも言わないでもこちらの意図を解してくれる。ソドップ調査隊の証については、広島カープファンなのかな? どうかな? 次項参照のこと。
レッドヘル
通称赤ヘル。すみません、野球のことほとんどわからないので、これといってよくわからないまま入れてます。正直、赤くて頑丈な帽子ならなんでもよかったのかも……。
ゴリラ
ソドップ編に入ると聖地の山がこいつに埋め尽くされる。以前に国外編の敵は現金を落とさないって書きましたけど、そういやこいつだけ5リラを落とすんじゃなかったでしたっけ。
巨人ソドップ

心優しき巨人。アンクルオン研究所から自由を求めてホーリーナイトと一緒に逃げ出しますが、最終的にマームに一撃で屠られます。気の毒に。ロストマンとは仲がよかった様子。名前の由来はBUMPの隠しトラックから。「*Reprise」にジミーの夢の中でシルエットだけ登場してます。
トラ
地上で最強の敵。アンクルオン研究所に入る前にこいつを倒せていない場合はトゥルーエンド未達フラグですね。こんな強い動物を一瞬で倒しちゃうマームの戦闘力すごい。
墓守
「アワナビーキコウシハン」でおなじみの墓守さん。この人を探してあちこちウロウロさせられるイベントは実は割と早いタイミングでショートカットできます。墓守を探し始めたくらいのタイミングでゴールの洞穴に行けばいいです。
GODZILLA
ゴジラ、すなわち松井秀喜使用モデルのレプリカ品です。地上ではこれが最強武器。
エコ研の人
世界に散らばった4つのメッセージボックスの中身の暗号を解読して、そのとおりの入力をすると入れるようになるエコロジー研究所の中でニコを待ち受ける人。エコ研の成り立ちやその悲劇についてはノベル「*Reprise」に詳しく書いてありますが、この人こそ「*Reprise」に登場する重要人物であるところのランプさんです(そんなに重要人物でもないな)。あ、ちなみに元生徒会副会長の弁護士カルマもレム市のその辺の道端にいますよ。
ゴミ(箱)除去装置
ゲーム本編だと単なるトンチキなネーミングの隠しアイテムですが、その裏には中編小説一本分の設定が隠されているという……夢と絶望と希望のガジェット。二度目のタンポポ丘の麓で手に入れるやつは、密航したジミーが持ってきたものなんですが、ナイ博士の形見をなんでここに置いて行ったのか……大地の声になんか言われたんですかね。
アンクルオン研究所の人たち
プレイヤーとしてはラストダンジョン的なものに乗り込んだつもりであろう場面で、微妙に優しい感じで応対してくれるし、なぜかこちらを気の毒そうにしてくるし、と混乱させてくる人たち。肩透かしでありながらも、この後ニコに襲いかかる辛すぎる現実をじんわりと予感させる、我ながら絶妙な演出だなぁ、と思う人たち。
アンクルオン
長寿な大博士。リリィのひいおじいちゃん。アンクル生物を生み出したすごい人、のはずなんだけど、単に例の石がすごいだけなのかもしれない。元ネタはBUMPの隠しトラック。ティンパストと対になっているのも元ネタ通り。歌を聴くとわかるけどだいぶ下品な言葉です。「*Reprise」の主人公四人の名前ジミー、マーカス、ゴードン、ジェロニモも同じ元ネタ。
ペニー氏とティンパスト教団の人
設定上、ティンパスト教団はアンクルオン研究所と完全に相対的な関係で、どっちがいいとか悪いとかはないはずなんですが(というかどっちもマッドネスですね)、「*Reprise」まで含めるとティンパストのほうがだいぶ悪役の要素が強くなっちゃいましたね。宗教と科学、いずれにおいても正の面と負の面があると思うのですけど、両面描いた(つもりの)科学に比べて、宗教側は負の側面ばかり描いちゃって、ちょっと申し訳ない気持ちです。宗教嫌いとか言いながら下手にスピリチュアルなんかに触っちゃうよりかは三大宗教のどれかをきちんとやってるほうが危険が少なくていいと思うんですけどね。ちなみにぼくはフライングスパゲティモンスター教の司祭の資格を持っています。
フェンリル(幼体)
神様も欲しがる、最強のアンクル生物。これを異世界に運びたいがために、偽ラフ・メイカーであるところのロキはあの手この手をつかって五つの石がこの場に集まるように仕組んだというのが、ニコの冒険の一つの意味なのですが、ゲームの仕様上、石いっこも持ってなくてもニコこの場に来るよねっていう(笑)。ちなみにニコの持ってない石はロストマンが回収して持ってる設定です。
ロキ
偽ラフ・メイカーの正体。なんかマイティ・ソーというかアベンジャーズですっかり有名になってしまった北欧神話の神様。原典からしてトリックスター的な性格で、ラグナロクでは神々を裏切ります。ちなみに物語後半に北欧神話が混ざってくるのはBUMPのアルバム『ユグドラシル』のテーマが北欧神話だったから。あ、あともちろん古いところで『グングニル』も北欧神話ネタですね。なお、うちのロキの性格とかセリフは、まちたびの試験公開版サイトのBBSを荒らしてたキッズにインスパイアされて完成しました。サンキュー、荒らしキッズ!
チャマ長老
ちょっとエキセントリックな人。うがーうがー。名前の由来は言うまでもないですけどBUMP直井氏の愛称チャマから。唐突に武田鉄矢の歌の歌詞を叫んだりする。ちなみに武田氏は『ラフ・メイカー』(楽曲の方ね)のファンであることを公言しているので、ぎりぎりBUMPネタだと言えなくもなくもないです。
キバ
まちたび最強のザコ敵。これはいったい……なんだろう……? 生き物じゃなくて、悪しきモノの概念……? みたいな感じのやつ。見た目ではわからないんですが強と弱、2種類います。戦ってもいいことないので、道端のトンガリに触って、どんどん消しちゃいましょう。
インベーダーキャップ
まちたびのプレイヤー層にはまるで響かないことを承知で放り込んだ「ゲームセンターあらし」ネタ。赤い帽子で最強というとこれしか思いつきませんでした……。
王のバット
これもまた、たぶんまちたびのプレイヤー層には響かないですね。世界のホームラン王、王貞治のバット。いやだからなんで最強装備がどっちも昭和ネタなんだ……。
鼻眼鏡
超々重要アイテム。これを持った状態でエンディングに到達するとトゥルーエンドが見られる……わけではなく、そのヒントが得られる…………って、今書いてて思うのは、ノーヒントからのヒント小出しで、どんだけ周回さすねん、クソゲーか!っていうね。でもそのおかげでみんなの心に残れたんだとしたら、クソゲーもまた名作の条件のひとつの形なのかも知れないな、と、ぼくが愛してやまない「たけしの挑戦状」のことをほんのり脳裏に浮かべながら思ったりもするのです。
本物のラフ・メイカー
こっちが本物。とはいえ原曲の歌詞っぽいこと言ってたのはずっと偽物の方で、本物のセリフはちょっとオリジナルが入っちゃってます。でも、ぼくの中でこのキャラは藤原基央その人のイメージ。ギター弾いて欲しかったし弾かせてあげたかった。
トネリコの枝と花の女神フレイヤ
あ、バットはこっちが本当の最強装備でした。花を踏まないでここまでたどり着いたあなたに花の女神フレイヤからの贈り物。なかなかわかって貰えなかったんですが、これかの有名な神槍グングニルですよ。神話ではオーディンがトネリコの枝を削って作ったと言われています(諸説あり)。ニコの武器はバットなので、槍じゃなくて枝ならぎりぎりバットっぽく扱えるかなぁーって。うん、いや、ちょっとよくわからんですね。ところで、どこかに書かれていたこれについての感想に「最強武器取った後、ろくに倒す敵がいないのでつまらない」というのがあって、ぼくは他のゲームやってても全然そういうことを思ったことがなかったのでちょっと驚きました。強い武器を手にしたらやっぱり誰かに向けたくなっちゃう人っているのだなぁ、だからこの世から戦争はなくならないのだなぁ、とも。トゥルーエンド近くまでまちたびをやった上でそう思われるっていうのは、要するに物語がその人の思想に敗北してるんですよね……、次、また頑張ります。
ダニーの霊
ニコの飼っていた犬で、庭には彼のお墓がありますが、初期案の導入部を削ったせいで初見ではあのお墓がなんのことかさっぱりわからない大問題が。BUMPファンならなんとなくピンと来るものではあるのですが……すみませんでした。最序盤の行動が最終盤に実を結ぶ、花と同じくらいロングパスなトゥルーエンドフラグの一つ。
オーディン
ロキに洗脳されて記憶を消されていたとおせんぼオジサン(←今名付けました)の正体。本当は研究所地下からユグドラシルに渡る時にブレイバーとはぐれて「異世界編」というのを描く初期案があって、海モチーフのBUMPの楽曲は、そこでネタの消化をするつもりでした(だから『sailing day』も『グングニル』も『三人のおじさん』もまちたびに出てこないんです)。次元の狭間に落ちたニコは過去の世界の海辺の村にたどり着き、そこではオーディンとロキが、幼名のオジンとロプトと名乗っていて、ニコはその二人と友だちになった上で一緒に長い長い航海の旅に出ます。そして大冒険の果てにユグドラシルにたどり着いたところでニコは現在の時間軸に戻ってくる……という、終盤に挟み込むには壮大過ぎる展開だったので、ばっさりカットしました。ちなみに今までどこにも言ってなかった裏設定がありまして、何を隠そう、この人こそがなんとニコのお父さんなんです。本人たち含め、作中それに気づいているキャラは誰もいないんですけどね。
フェンリルと百人アルエ
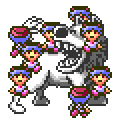
百人? いやいや設定にはそう書いてあるんですよ。フェンリルはほとんど喋らないんでなんだかよくわからない奴。トネリコの枝でひっぱたかれてもへっちゃらな超頑丈な奴。ニコの手を汚さずに物語からロキを片付けることができたのはこいつのおかげです、ありがとう。エンディングで百人アルエと一緒に軌道周期(『orbital period』まちたび作ってる時は未リリースでしたけど)に乗りました。宇宙からリリィママの眠るタンポポ丘を見守っています。
おしまい!
エンドマークをなんて書こうかな、みたいなことで悩むことができるのが、ゲーム作り終盤のなによりのお楽しみだったりします。作品の締めくくりをどこの国の言葉で、どんな字体で、なにを背景に、どうやって画面に出そうか? いろいろ考えてピッタリくるものを当てはめられたなら、そのあとずっとハッピーでいられるかも……なんて。まちたびの場合は、いろいろ考えた結果、日本語でかわいく、抜けるような青空をバックに、一文字づつぽんぽん表示するようにしました。話はちょっと変わりますが、ぼくは物語とか小説とかの後ろに載ってるあとがきとか解説とかすごく好きなんですけど、作家さんの中には「自作の解説などという野暮なことは控えるべく、ここは早々に筆を置く」みたいなことを書いちゃう人もいて、そういう寂しいあとがきを見かけた時にはいつも心の中で「いつかもし自分が作品を作ったなら、無粋と言われようと、みんながもういいやめて!と叫びだすまであとがきを書き続けてやるぞ、それがたとえ本編よりボリュームが大きくなろうとも!」とか思っていたものです。そしてついに自分の作品をこうして公開して、あとがきページを設置した時に、その思いを叶えるべく延々と終わりの来ることのないこの「カーテンコール」を書き始めました。このページの冒頭に書いた「この作品を愛してくれたすべての「あなた」にありったけの愛を込めて、オマケを」という言葉にはそんな野望が込められていたわけです。ありったけの愛が重い! 年月的に! 実にそれから15年近くも、延々と、だらだらと、この「カーテンコール」を更新し続けてきました。まあ日々の暮らしの中ではちょいちょい存在を忘れてるんですけど、この作品のことを好きだって言ってくれる方々がわりと途切れることなく現れ続けて(エゴサーチ!)、ぽつりぽつりと連絡をもらったりするタイミングがあると、そういった度に、ここ(あとがきページ)のことを思い出すんですよね……。えーっとつまりなにが言いたいかというとですね、その間、人生では山あり谷あり色々起こってはいたんですけど、このあとがきに触れている間、この作品のことを考えたり書いたりしている間、ぼくはずっとずっとハッピーでしたよ! っていうことです。特に「あとがきも好きです」とどこぞに書いてくれたあなた、どうもありがとうございます。ここにある文章はすべてあなたのものです。さてさてさて、そうしてずっと書き続けてきたこの「カーテンコール」もついに終わる日がやって参りました。主要なキャラとアイテムを解説しつくし(たぶん)、元ネタのほとんどをツマビらかにし、物語を全部語り直して、こうしてもう一度、元の物語と同じエンドマークに辿り着いたのです。すごく長い時間だったはずですけど、全然長くなかったなぁー。それよりか、むしろまだまだなんか書き続けられそうな気がするなぁー。とは言え、それはなんかそんな気がしているだけで、さすがにもう書くことはないのですね。ここで本当に終わります。時の最果て、終わらないカーテンコールの終わり――野暮と無粋を踏み越えて、語り尽くしたまちたびの、ほんとにほんとの大団円! 間違った旅路の果てに正しさを祈りながら、またいつか別の作品でお会いできる機会があることを願っています! てゆーか頑張ります……(『ジタクケイビ』のこともたまには思い出してあげてください、、、笑)
「バイバイ! バイバーイ!」
『いつまでもみんなのことを愛してる』!
――書類はニコの手の中で音もなく崩れ去った
自作解題
開発のきっかけ
『間違った旅路の果てに正しさを祈る』のシナリオは、ノベルゲームを想定して書き溜めていたメモが元になっています。
創作の初期衝動は、ロックバンド“BUMP OF CHICKEN”の物語性豊かな詞の世界を、クロスリンクさせ、ひとつの世界にまとめた、箱庭的なものを作りたいという欲求でした。要するにアーティストとの一体化を願う「痛いファン」の代償行為そのものでしかないのですが、ゲーム的な演出に全力を傾けることで、ひとつの作品として成り立つのでは、という読みはありました(その目論見がうまくいったかどうかはプレイヤーのあなたがどう感じたかによります)。
「bumpofchiken.txt」というあまりにまんまなファイル名を持つそのメモを、ぼくがいつ頃から書き始めたのかはすでに記憶が定かではないのですが、2005年の冬頃には現在公開している完成版のストーリーと同じ展開を持つ物語の大筋は出来上がっていました。若干異なる点としては、冒頭の導入部が、メモの段階では「飼い犬のダニーが死んでしまい、ひとり部屋で泣いているニコの元にラフ・メイカーが現われ一緒に泣く」ところから始まって「リリィとの天体観測」につながるのに対し、完成版ではプロローグの文章のあと、いきなり「天体観測」から入るようになっています(出だしをなるべく明るい雰囲気で始めたいという判断によります)。
構想していたノベルゲームとしての製作からRPGとしての製作への転換は、2006年4月、開発に着手するべくノベルゲーム製作ツールをネットで検索していた時、ひとつのゲームを見つけたことから起きました。
ドラクエ調WWA『WWDQ』。
『WWDQ』は非常によく出来たゲームで、製作者に対してリスペクトとともにライバル意識もわきました。「ドラクエのWWAがあって、MOTHERのWWAがないなんて……くやしいっ!」 それがマザー調WWA製作の直接のきっかけでした。
(RPGとして完成させた今でも、吉里吉里で製作された『間違った旅路の果てに正しさを祈る』を見てみたい気はします。自分ではもう絶対作らないけど)
WWAについて
『WWDQ』をプレイすることでWWAマップツールの存在を知ったぼくは、そのゲーム製作ツールとしての優位性を強く感じました。
確かにWWAマップツールはRPGツクール等のツールに比べて機能が乏しく、市販のRPGのような完成度を持った作品を作るのは不可能です(システムバトル等の工夫を凝らしたWWAを作っている製作者の皆さんには申し訳ありませんが、ユーザーインターフェースの不自由さなど、現実問題としてそう言い切れます)。
これは元々のコンセプトがいわゆる「RPG」の製作ツールではなく、それとは別の意味を持った「インターネット指向型RPG(ぼくは正直、その意味するところはよくわかっていません)」の製作ツールであるためだと考えられますが、そのコンセプトにより(あるいはまったく関係なく)、WWAには他のツールにはないふたつの大きなアドバンテージがありました。
まずひとつめに、これが(製作者の意図したことかどうかは知りませんが)おそらくRPG製作ツール史上初のオブジェクト指向の製作ツールであるという点。
MOTHERシリーズの生みの親である糸井重里氏は『MOTHER3』の開発初期段階に「ハードボイルドの探偵物語的な、街を主体としたゲーム」を構想し、従来型のロードムービー的演出から脱却しようと画策していたといいます(ある程度のゲームマニアなら、それってなんてポートピア連続殺人事件? と思わなくもないところですが、要するにRPGのインターフェースのまま探偵モノAVGっぽい世界観のゲームを作りたかったのではないかと思われます。『moon』や『U.F.O.』などのラブデリック系ゲームに近いモノかもしれません)。
それは「ひとつの街という限定されたマップ内でプレイヤーが行動し、その行動(あるいは単純に時間の経過)によって、住人たちが次々とリアクションを変化させていく」というシステムによって表現されるはずでしたが、実際のところ、構想から10年以上経て発売された『MOTHER3』では、「地理的には同じ場所」という設定でいくつかの異なるマップを用意して、「時代ともに成長していく村」という表現に替わっており、構想段階での「部屋散らかして旅行に行ったら、帰ってきたとき部屋散らかったまま」というシステムは採用されませんでした(ROMカセットでは無理ということらしい。幻の64DD版では実現できていたようではあります)。
なにが言いたいのかというと、実はWWAマップツールで製作されたゲームは、誰がどう作ろうと「部屋散らかして旅行に行ったら、帰ってきたとき部屋散らかったまま」のシステムを持つ、いや、持ってしまう、ということです。
糸井氏がかつてRPGの新しい形として構想した「拾う捨てる傷つけるといったプレイヤーの行動があとあとまで残る世界」は、今や小学生御用達のツールでいとも簡単に実現できてしまうのであります。
これはWWAマップツールの持つ特異なシステム(というよりむしろ、より現代的なシステムというべきなのですが、それについては後述します)に起因するものと言えます。
一般的にRPG製作にはフラグ(あるいは変数)といった概念が必須であります。すなわち、プレイヤーがAという行動を取った際に変数aに正を代入しておく(フラグを立てる)。イベントBは変数aを参照し負(フラグが立っていない)ならイベントCに移行し、正(フラグが立っている)ならイベントDに移行する――云々、という概念です。
しかしWWAマップツールのシステムにはフラグという概念は存在しません。代わりにあるのは「物体」「背景」といった二種類のオブジェクトであり、オブジェクトは他のオブジェクトを出現させたり、消失させたりすることができる。すなわち、プレイヤーが「番号1」の「物体」に接触すると、「番号2」の「背景」が座標(x1,y1)に出現する。「番号3」の物体に接触すると座標(x2,y2)の「物体」が消失する――。
他のツールになれた人間にはクセのあるシステムではあります。「WWAにフラグのシステムがあれば便利なのに」そんなユーザーの声も存在します。ですがJAVA言語を含む現代的なプログラム言語はほとんどすべてがオブジェクト指向の言語です(オブジェクトの意味は若干異なる)。ゲームの製作ツールがそれに倣うことは、時代の必然とは言えないでしょうか?
ぼくはこのシステムからの発想がまったく新しいタイプのRPGを生み出す可能性を秘めているのではないかと、強く感じたのです。
そしてふたつめ、これがブラウザゲームの開発ツールであるという点。
通常、ゲーム製作ツールで作られた作品をプレイするには、実行型ファイルやデータファイルのすべてがHDD上に存在している必要があります。つまりダウンロードした圧縮ファイルなり、CD‐ROM等のメディアなりから、ゲームを「インストール」および「セットアップ」しなくてはなりません。
もちろんゲームにしろ、それ以外のアプリケーションにしろ、PC上で動作するプログラムの大半はインストールの必要があるのですが、その手順は時として面倒であり、動作環境や必要な外部ライブラリの確認などについては(特に初心者にとって)大きな心理的障害となりえます。
翻ってWWAは、JAVAアプレットを利用したブラウザゲームです。インストールもセットアップも必要なく、JAVAの実行環境さえあれば、PCのアーキテクチャさえ問いません。
プレイヤーは「ふだん使っているブラウザ」で、「サイトを閲覧するのと同じよう」に、ただ「ページにアクセスするだけ」でいいのです。それだけでゲームがプレイできます。この敷居の低さが持つ意味の計り知れなさを、多くのWWA製作者はあまり明確には意識していないのではないでしょうか。
例えば近頃Googleがやっきになって行っているWEB上でのアプリケーションサービスなどについて考えれば、WWAの持つ先進性はおのずと明らかでありましょう(FLASHでなくJAVAアプレットであるあたり、むしろ早すぎたと言えるかもしれない)。
以上の点から、ぼくは製作のためWWAマップツールを採用しました。小学生のおもちゃとして留めおくには、あまりにもったいのないツールだと言えます。
タイトルのこと
ゲームの名前としては少し長すぎる『間違った旅路の果てに正しさを祈る』というタイトルは、“BUMP OF CHICKEN”の楽曲『ロストマン』の詞の一節に由来しています。
試験公開の当初よりお付き合い頂いた方はご存知かと思いますが、元々このタイトルは仮のものであり、表記も『間違った旅路の果てに正しさを祈るRPG(仮題)』となっていました。実を言うと構想初期の段階ではこのタイトルはキャッチコピーのつもりだったのです(余談ですがBUMP OF CHICKENがテーマソングを提供し、ボーカルの藤原氏が作中曲の作曲を担当したPS2用ゲームソフト『テイルズ オブ ジ アビス』のゲームジャンル(!)が「生まれた意味を知るRPG」であり、それはテーマソングの『カルマ』の詞の一節に由来しています)。
タイトルは試験公開期間中に考えて決定するつもりでしたが、なかなかいいタイトルが思いつきませんでした。
ゲームタイトルの条件は、個人的な考えですが、覚えやすさと親しみやすい語感、そしてインパクトだと思っています。できる限り短いほうがそれらの条件に合いやすく、もし短くできないなら、省略のしやすさで補ってもいいでしょう。
候補としては『NICO』や『ニコリリ』、『ファイブストーン』などがありました(いやウソです、最後のは今考えました)。覚えやすさや語感については問題ないと思いましたが、どうにもインパクトに欠け、決定とはなりませんでした(ご承知のとおり、ニコリリは今ハンドルネームとして使っています)。
そうこうしているうちに、試験公開ながら『間違った旅路の果てに正しさを祈るRPG(仮題)』はネット上でそこそこの評判となり、いくつかのサイトで紹介され始めました。
紹介して頂けるのは製作者冥利につき、非常に嬉しかったのですが、思いもよらずたいていのサイトで(仮題)が無視されていました。またBBSなどで話題となった場合も同様で、いつの間にかネット上では(うちのサイト以外――笑)『間違った旅路の果てに正しさを祈る』が正式なタイトルとして扱われるようになっていました。
ネットで一度広まった情報は(合ってるしろ間違ってるにしろ)一次発信者にさえ制御できない、というのは誰でも知っている事実でしょう。いまさら『NICO』だの『ファイブストーン』だのとタイトルをつけたら、新作と勘違いされかねませんでした。
そしてぼくはあきらめ混じりにタイトルから(仮題)をはずしました。
何度か口に出してみると、思いのほかこのゲームのタイトルにふさわしい気がしました。問題らしい問題は長すぎるという点だけです。元は天才詩人藤原氏の歌詞であり、インパクトについてはまったく申し分ありませんでした。
今ではもう、これ以上このゲームに合ったタイトルがつけられる気がしません。とても気に入っています。
#ちなみに省略形として『間正(ハザマタダシ)』というのを考えたのですが、皆さんおおっぴらに喧伝しないようにお願いしたいところです。きみとぼくだけの合い言葉だよ、いいね?
##なーんて冗談言ってたけど、「まちたび」っていう略称がいい感じに浸透してきてるんでこのまま「まちたび」で行こう! aruさんありがとう!
ロストマンのこと
タイトルの由来ともなったBUMP OF CHICKENの『ロストマン』という曲の歌詞の世界観を、ドラマチックに拡大解釈したものが、このゲームの物語の下敷きになっています。
BUMPの曲は聴き込めば聴き込むほど多様な解釈ができる可能性を持った世界観を持っているのですが、物語を作るうえでぼくはあえてその多様性を廃し、一本の筋道として「僕」が「君を失ったこの世界で」、「間違った旅路の果てに正しさを」祈るというストーリーを組み立てました。
歌詞の「僕」と「君」がそれぞれ「ニコ」と「リリィ」に対応しているのは言うまでもありませんが、少しややこしいのが「ロストマン」というキャラクターについてだと思います。
楽曲『ロストマン』では、まず第一に「君」を失った「僕」がイコール「ロストマン」であるという解釈が成り立ちますが、それとは別に歌の後半部で「僕」が「ロストマン」に対して呼びかけ、語りかける場面があります。
自身「ロストマン」であるはずの「僕」が語りかけている「ロストマン」とはいったい誰なのか? このゲームでは、そのひとつの解釈として「もうひとりの自分」という設定を考えました(もちろん、これが正解の解釈だと思っているわけではありません)。
「もうひとりの自分」という言葉についても実際いかような解釈の仕方もあると思うのですが、いちおうロストマンについて製作者が考えた設定は、主人公ニコの対となる存在、(表と裏、光と影のような対象さとはまた違った)隣り合わせに並び立つ存在でした。
ロストマンというキャラクターについてゲーム内で語られるのは、アンクルオン研究所に、そのスポンサーである軍から派遣され、人体実験を受けた強化人間であるという設定と、ろくでもない人間ではあるが、どうしても憎めない人物であるという設定です。これについて語るアンクルオン博士の台詞は、彼がロストマンを強化人間にしてしまったことへのちょっとした罪悪感を表わしているとともに、ニコがファーストコンタクト時に受けた印象ほど、ロストマンが邪悪な存在というわけではないことを伝えようとしています。
ロストマンの生い立ちや趣味や主義は特に決めてありませんが、ひとつだけはっきりと決めてあったことは「彼がかつて恋人を失っていて、彼女との再会を望んでいる」という設定です。
それはちょうどアンクルオンに辿り着いたニコが迎える状況とぴったり重なり合います。そして彼らはふたりとも優れた戦士としてロキに目をつけられ、手駒として誘導されています。
世界樹に入ってからは互いがいつ入れ代わってもおかしくないほどにふたりの運命は近いものとなり、最終的には旅の仲間として決戦の地へ向かうことになります。
ちなみにロストマンが失った恋人の名はユリという名に設定してありますが、もしかしたら本当はリリィという名前であったかもしれません。
というのは、あのロストマンという少年、実は未来のニコの姿かもしれないという(絶対に表には出ない裏の)設定があるからです。
このゲームの世界はとにかく時間軸の扱いがあいまいで、過去現在未来がめちゃくちゃに混ざり合っています。
物語冒頭にニコとリリィが見ていたほうき星はラスボスのフェンリルなわけですが、本来の時間軸のフェンリルは、あのタイミングではアンクルオン研究所で、いまだ胎児の姿でカプセルに入っているはずです。また、ニコが公園のブランコで出会ったアルエは、ゲーム後半、アンクルオン研究所の地下でニコを救って時空ジプシーとなったアルエが、それ以降の長い長い時空の放浪の末、最期に辿り着いた瞬間のアルエですし、未来からやってきてニコの手助けをするブレイバーは、ゲームエンディング以後、さらに十数年経った後のブレイバーだったりします。
そんな中であれば、未来の主人公が現在の主人公の前に登場したとしても、不思議ではありません。
幸運にもプレイヤーの操るニコはロキの指輪の餌食にならずに済みましたが、もしあそこでロキに心を受け渡していたとしたら。リリィを蘇らせたいばかりに、正しさを祈ることを忘れ、ただひたすらに間違った旅路を邁進し続けたとしたら――。
ニコは最終的にリリィの死を受け入れ「選んできた道のりの正しさを祈った」がゆえにトゥルーエンドでファーストのアルエと再会しますが、道を誤ったことを知りながらあえてそれに目を瞑ったロストマンは、それ以上恋人の面影を追うことは(運命論的に)許されずアンクルオン研究所に戻ります。彼は研究所で決して不幸ではありませんが、一生埋まらない心の隙間を抱えて生きていくことでしょう。
「ロストマン」とはそんなニコのif的存在である可能性を持ったキャラクターでした(ゲームではほとんどわかりませんね。失敗、失敗)。
ギャグとユーモアのこと
「まちたび」の個々のセリフを作っている時にいつも思っていたのは、「ギャグではなくユーモアでプレイヤーをにっこりさせたいな」ということでした。ぼくは日頃からギャグとユーモアについてはかなり厳密に分けて考えるタチで、その二つでは断然ユーモアのほうが好きなのです。
まあ完成した「まちたび」をプレイしてみると、思ったよりユーモアが足りてなくて改めて自分のセンスのなさや力不足を目の当たりにしたりもするわけですが、それはそれ、これはこれで。
ギャグとユーモアの違いについて詳しいことが語れるわけではありませんが、ぼく自身のものすごくおおまかな捉えかたで言うと、ギャグとは場当たり的で前後との関係性が薄い「受け狙い」のことで、ユーモアは逆にTPOや前後との関係性に依存した「受け狙い」のことではないでしょうか?
そう考えると必然的にユーモアには極小サイズの世界観と時間軸が存在していることになり、それはすなわちひとつのユーモアにはひとつのドラマがあるということになります。
逆に言うと、ギャグならポーズなり言葉なりを思いつけばそれで完成なのですが、ユーモアを表現するにはミニマムなドラマをひとつ組み立てなければならないということでもあります。コスト的にはユーモアのほうが手間暇がかかるわけです。
ではどうしてそんな手間暇をかけてギャグではなくユーモアでセリフを考えていたのかと言うと、それはキャラクターの個性を作り、それをプレイヤーに伝えるためなわけです。人を楽しませながらキャラクターの個性を描写するためにはどうしてもユーモアが必要で、ギャグではその用を成しません。
例えで言うと、小島よしおの「でもそんなの関係ねぇ!」は動きと言葉だけ見るとギャグですが、「でも」の前段階の自虐ネタとの関連性から言えばユーモアでもあるため、彼がどんな人物でなにを考えているのかといった情報が一定量得られます。しかしレイザーラモンHGの「フォー!」は完全にギャグであるため、彼がどんな人物なのか、そのギャグひとつではさっぱりわからないのです。
登場人物のセリフにユーモアを含ませる作業は、そのキャラクターに命を吹き込む作業だと思います。それは(話を早く進めたい語り手にとっては)時として面倒だったり時間がかかったりするものではあるのですが、人の心を動かそうと試みるならば、人間(擬人化された動物や器物も含む)というものをきちんと描く必要があると思うのです。
ぼくはそのあたりの作業というか工程を丁寧にしっかりと踏んだ作品がやっぱり好きで、本当は「まちたび」にもそういう作品になって欲しかったのです。